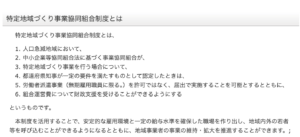こんにちは!農家ハンター応援団 フォトライターの髙木あゆみです。
2025年6月、農林水産省の職員の方々が、プライベートで研修にお越しくださいました。今回は、その現場でのやりとりや学びをレポートします!
この日お越しくださったのは、農林水産省よりお3方。
-
九州農政局 谷川 智雄さん
-
九州農政局 玉城 寛人さん
-
本省鳥獣対策室 佐藤 駿悟さん(東京から!)
仕組みを作る側、日本の鳥獣対策の“ど真ん中”にいる皆さんです!
【レポートのポイント】
▶︎三角町の鳥獣被害対策
▶︎ジビエファーム・解体施設運営のリアル
▶︎狩猟文化の有無
▶︎箱罠の選び方と注意点
▶︎柵設置のコツ
▶︎イノシシパウダー化マシーン
▶︎まとめ
2024年度は、全国的に捕獲頭数が多かったそうです。農家ハンターの本拠地・宇城市三角町の2024年度のイノシシさん捕獲頭数は1016頭と過去イチです。
三角町の鳥獣被害対策
狩猟文化の有無
三角ではもともと捕獲文化がなく捕獲技術を持った人が地域にいませんでした。
農家ハンターに当初から多大なご協力をしてくださっている大師匠・山本さんが三角じゅうを回っていて、それを引き継ぐように稲葉たっちゃんと井上くんが取り組んできました。
それから時間をかけ、住民自身が捕獲できるように技術を共有してきました。
いろんな地域で話を聞くと、もともと狩猟文化があるところは動物がいる環境も食すのも当たり前でした。対策に従事する人もいて、そこまで困っていない印象があるそうです。
狙いは動物たちの「絶滅」ではなく、「山から人里への出没数を減らす」こと。
“濃くなった部分を薄める”という感覚が大切です。
解体施設運営のリアル


捕獲頭数が左右する運営の難しさ
ジビエの解体処理施設であるジビエファームは、農家ハンターから生まれた株式会社イノPが運営しています。この解体施設をつくる費用を確保するために会社を立ち上げて今に至ります。実際にやってみて、直面した課題がいくつかあります。
-
季節によって変動する捕獲数
-
売れる肉と売れない肉の差
-
味と品質の維持
-
食肉にならない部位(残渣)の処理先の確保
残渣の処理は、どこが引き受けてくれるかは自治体によってまちまち……
家畜ではないのと民間施設の解体処理施設であることから処理先の確保が一筋縄ではいかず非常に大変だったようです。
捕獲が増えると、「命を無駄にしたくない」という想いから、解体施設の設置やジビエ利活用をする動きが出てきます。
命を無駄にしたくないという思いの表れだと思います。
しかしこれまでの経験から、有効活用・利活用したい気持ちは重々わかるものの解体施設をつくるのは慎重に、と稲葉たっちゃんは普段から伝えています。
ジビエ活用までのおすすめフロー
ジビエ活用までのおすすめフローはこちらです。
減溶化設備を整える(イノシシさんを5時間でパウダー状にします。堆肥としての活用を検討中)
↓
どのくらい、どんな個体が捕獲されるかを知る
↓
解体施設をつくっても採算取れるか?
肉の取引先はあるか?
残渣はどこが引き取ってくれるか?
人的経済的に運営できるか? を検討
↓
見通しがたてば解体施設をつくる
現場で見た!箱罠の選び方と注意点

箱罠には多様な種類がありますが、重要なのは「どんな個体を捕獲したいか」によって適切なタイプを選ぶこと。
-
感度が高すぎるとウリ坊だけがかかって親を逃してしまう
-
取り逃がした親は二度と罠にかからないことも
「獲りたい個体に合わせた罠選び」が捕獲率を高めます。


止め刺しと電気ショッカーの選択肢
現場での精神的負担と対策
止め刺しの道具、電気ショッカーも実際に持っていただきました。


捕獲にかかる最大のハードルが止め刺し。
狩猟とは違い、有害鳥獣対策のために捕獲する人は「獲らなくていいなら獲りたくない殺したくない」という思いを持つことが多いです。精神的ストレスが大きいため、止め刺しの方法は負担が小さいことが重要です。槍をつかうところも多いですが簡単ではありません。そして心身ともにすり減ってしまうという経験をたっちゃんも井上くんもしてきています。
空気銃は人間にも動物にもストレスがありません。が、銃を持つのは簡単ではないので、やはり電気ショッカーが扱いやすいです。
手作りする人もいますが、それだと電気が流れていることが分からなかったりしてヒヤリハットが多いため、安全面に配慮されたものを購入することをおすすめしています。
柵設置のコツ:メッシュ柵と金網柵
メッシュ柵の設置方法
メッシュ柵は害獣対策をしている地域ではどこでも見かけます。ブログでも何度か取り上げていますが、その向きは裏表が逆になっていることも多く、どうやら納品の仕方に原因があるようです!
納品時、表・裏・表・裏とたがいちがいに重ねてあるそうです。重ねてある通りに設置すれば、たがいちがいの柵になってしまうというわけです。
「納品の仕方を変えてもらったらいいのでは……」とわたしは思いましたが、コンパクトにするためには致し方ありません。

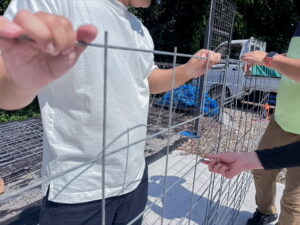
両端を隣の柵と1マス分被せるのも重要です。
害獣たちは畑に入れる抜け道をぐるぐると回りながら探し、「ここ弱そう、いけるかも」な場所があれば掘ってすり抜けようとがんばります。その隙を与えないようにするために、両端を重ねて守りを固めます。重ねることを計算に入れて、必要数を調達する必要があります。
金網柵
ゴリ押しなのが金網柵です。地面の状態に合わせて張れるため、隙間ができません。L字で張るので、動物が掘って中に入ることができないためです。人手や手間はかかるしコストもかかります。でもその分効果があります。しっかり張れば動物の侵入も、食害によるストレスもありません。
全てを金網柵で張るのはコスト面で難しい場合、地面がごつごつ/凸凹した場所は金網柵にし、それ以外はメッシュ柵にするなどして場所ごとに検討してもいいでしょう。
減溶化施設「イノシシパウダー化マシーン」
総重量400kgを一度に、まるごと処理できます。
休眠預金を活用して導入した、新イノ粉マシーン。解体に向かない個体、肉にならない部分の処理の行き先としてはもちろん、この減溶化マシーンの運用をしていくことで、地域で鳥獣対策する人の後押しもできます。
止め刺しとその後の処理が2大難関の害獣被害対策。山での埋設処理が多いですが、国の研究機関が作成したガイドブックによれば、
150cmを掘る……想像できますか?汗だくで体力も時間もすり減ります。わたしはたぶん、ぶっ倒れます(・∀・) 施設はその処理を担ってくれます。
無機質と混ぜて堆肥とすれば、畑への散布や販売の道も見えるかもしれません。



古石さんのいちじくハウス
TOBASE Island Works代表の古石さんのいちじく農園も訪ねました。いちじく栽培についてや特定地域づくり事業についての意見交換などしました。
(特定地域づくり事業についての取り組みはこちらをご参照ください https://farmer-hunter.com/blog/5332
特定地域づくり事業によって就農者を増やしたり地域の人口減少を食い止めたいという思いがあると古石さん。
いちじくが実っている様子を見るのは初めてで、3ヶ月でこんなに大きくなるんだ!と驚きました。


柿の木の下で、ヤギを眺めながらのまとめ
宮川洋蘭の柿の木ガーデンで、クロストーク。
ヤギを眺めながら……というよりもヤギも混ざってきていました。
今回はスケジュールはある程度決めていたものの、聞きたいことに合わせて時間を調整しました。ジビエファームで2時間も話したのは初めてでした笑

政策をつくっていく皆さんです。
質問する姿勢や内容、まなざしから熱意が伝わってきました。
公も民も一緒に、ですね。今回のプライベート視察が政策に活かされていくことを願っています。