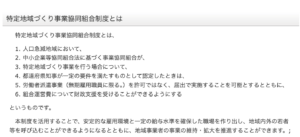農家ハンター応援団 フォトライターの髙木あゆみです!
2025年8月、彼らの現場で見て感じた事をレポートします。
阿蘇市のある地区にて、840mの通電シート(電線が織り込まれた防草シート)と電気柵を設置しました。
作業には地域の方約20名が参加。イノPからは稲葉たっちゃんと、特定地域づくり協定のメンバー・井手くん、JICAグローカルプログラムで研修に来ている竹村くん、橋本くんも加わりました。
当日の様子をお届けします!
==================
【レポートのポイント】
▶︎通電シートを設置
▶︎電気柵の支柱を設置
▶︎電気柵の電線張り
▶︎電気柵の電源装置の設置
==================
美しいカルデラでの早朝作業
阿蘇の美しいカルデラの中、夏の早朝に作業が始まりました。
地域の方によれば、すでにイノシシは出没しているとのこと。
まだ稲は食べられるほど実っていませんが、各所で足跡が見つかっています。山や川から、イノシシは静かに近づいてきているのです。
稲穂が実る前に、そしてイノシシが活発に動き出す前に——早めの対策が必要です。



① 通電シートを設置
まず通電シートを敷きます。
コンクリートから少し離すと通電効果が高まります。
位置を決めたら、杭で固定します。

場所のあたりをつけたら、杭で留めます。


杭を打ち込むのは難しくないですが、場所によっては地中が固く杭が入り込みませんでした。そんな場合はバール等を使って穴を掘ります。


② 電気柵の支柱を設置
杭を打ち終わったら、次は電気柵の支柱を打ち込みます。


③ 電気柵の電線張り
支柱を打ち込んだら、電線を張ります。今回はイノシシ対策のため、地面から20cm、40cmのところに2本設置します。
上から張ると2本ともたわまずにピンとなります。



井手くんも立派な戦力です!

人数が多い分、作業は順調に進みます。

こういうところは、見回りや草刈りの頻度がどうしても低くなりがちです。通電シートは価格が高めなので予算に合わせて部分的に利用するのもすすめています。

通電シートは、電線が織り込まれていることもあり価格は安くありません。草刈りがしづらいところなどで部分的に使用することも◎です。

電線の接続は結ぶだけでも可能ですが、通電効率を高めるため、電線の被覆をはがして直接結びました。ライターも現場で活躍です。

張り終えたら、地面からの高さが20cm・40cmになっているか確認します。これは効果的な防護のための重要なチェックポイントです。
④ 電気柵の電源装置の設置
最後に電気柵の電源装置を設置します。
管理者が操作しやすく、かつ動物や人が触れにくい場所が望ましいです。電気柵の内側に設置するのが良いそうです。


近くには子どもも住んでいて、今回、子どもたちがよく走り回っているところに電柵が設置されました。集落の方々は安全のため周知活動を行うことを話し合っていました。

写真では見えないところまで総延長840m。
シート敷き、杭打ち、ポール配り、高さ調整、電線張り。
大勢で取り組んだので4時間で終えました。暑かった〜!
大変お疲れさまでした!


先日、ソラシドエアさんと電気柵を張った経験から、若手3人も立派な戦力となっていました。