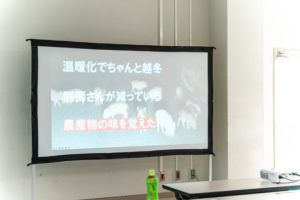農家ハンター応援団 フォトライターの髙木あゆみです!
彼らの現場で見て感じた事をレポートさせていただきます。
東京で働く、バリキャリな女子2人が農家ハンターにやってきました!
目的は、ジビエツーリズム。
東京から一泊で、濃密なジビエ2日間をお楽しみくださいました。
全編に続き、後編のスタートです!

女子会が盛り上がって遅かったので、朝はちょっとゆっくり目スタートです。
「いつもは寝つきが悪いのに秒で爆睡でした!!」
と元気な様子です✨
昨日植えた木々にお水をあげることから始まりました。

今奥にいる合鴨ちゃんも水をかけてもらってぐわぐわ喜んでおりました。
かわいい。

朝のアクティビティは、イノシシさんの革のクラフトワークショップ。
講師はさよちゃんです。
イノシシのどの部分を使っているのか、
革には野生のイノシシならではの傷があることなどをお話しして始まります。




イノシシが生きた証でもある傷を見たお二人、
「えー、愛おしい〜!!!」
なんて素敵なコメントでしょうか。慈しんでおられました。
そしてできたのは、キーホルダー。
お二人が何をモチーフにしたかというと…
昨日 見た夕日と月
だそうです!
思い出がこうして形になるってロマンチック✨

さぁ次はお楽しみの海釣りです。

キャプテン宮川の船に乗って、釣りに行きます。


三角のピラミッドを海から眺めて宮川キャプテン厳選の釣りスポットへ。


この日は大潮のうえに満潮、風は強く潮の流れは速いという難しいコンディションでした。船を止めるとどんどん流されます。
でも流れるのも、魚を待つのもまた楽しい!
竿を持つのも初めてという都会ガールでしたが、無事にガラカブちゃんが釣れました🐡


海の上は穏やかで、いつもとは違う時間が流れます。
波に揺られているだけで心地よいね、なんて話していた時にキャプテンから差し出されたベトナムコーヒーは格別でした。
普通のコーヒーではない、ベトナムコーヒーがまた合うんです!なんででしょう?

海からマリーナに戻るまで、ちょっと寄り道。
三角グルメを楽しみます。
完売直前に購入できた、STRANGEFRUITSのいちじくマフィン(絶品)!
農家でもある店主さんが作られたものなんですよ〜
絶品なはずです!

そして天ぷらも食べ歩き。

タコ天、エビマヨ天、ごぼう天、温かくて、最高の食べ歩きグルメでした。
お二人もとっても喜んでおられましたよー!
そして、おなじみの湊鮮魚店でお魚を刺身にしていただきます。

さばく技術が素晴らしくて見入ってしまいました。

お刺身を持って、鶴に帰ります。

鶴では、宮川さんが釣ったガラカブを揚げてくださいました✨
さっきさばいてもらったお刺身とガラカブをいただきます。



お二人があまりにおいしそうに食べるから、こっちまで見ていて幸せな気持ちでした。
お二人には”初めて”がたくさんの旅で、120%楽しんでいただけたようです✨
楽しい時間はあっという間に過ぎ、電車の時間が近づきます。
おなかいっぱいになったところで、鶴を出発です。




さよならを言って、三角駅へ。
三角駅のかわいさに、電車の旅を選んだお二人。

最後までおふたりで賑やかに帰られたのでしょう✨

おかげさまで、わたしも最高に楽しい、刺激的な2日間を過ごせました。
お友達といつもと違う旅をここで体験したら、
絆は深まる、思い出は多様で賑やか間違いなしです。
女子旅にジビエ、ありです!
実は、この女性2人は、楽天の社員さん。
宮川さんとは長いお付き合いがあります。
ご本人はパッション枠だとおっしゃってましたが笑、ここまで来て、喜びとともに体験に汗する方です。
仕事できないはずがない!ひしひしと伝わってきます。
またおいでくださーい!
楽天の社員旅行にもどうぞー!





























 「何これ美味しい!!!!!!」
「何これ美味しい!!!!!!」